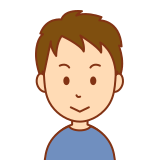
蝶は季節によって模様が違うと聞いたことがあるけど本当?
1年に複数回世代交代を繰り返す蝶は、産まれてくる季節によって模様が異なることがあります。これを蝶の季節型(きせつけい)といいます。
この記事では、蝶の季節型について解説をします。
蝶の季節型
多くの蝶は1年に何度も世代交代を行っています。”多くの”と書いたのは、種類によって違うためです。
例えばギフチョウは年1回発生(つまり年1回の世代交代)ですが、アゲハチョウは一般的に1年に4~5回程度世代交代を行います。アゲハチョウの場合、越冬した蛹から3~5月頃にかけて第1化が成虫に羽化し、その成虫が産卵し、第2化は5月~6月頃に羽化して成虫になります。この時、第1化は春型と呼ばれ、第2化以降は夏型と呼ばれます。一般的に夏型と比べて春型は小柄で黄色が鮮やかになる傾向があります。
アゲハチョウに限らず、様々な種で出現する時期により春型、夏型、秋型と呼ばれ、模様が異なります。以下では、季節型が明確に表れる蝶を何種類か紹介したいと思います。
季節型がある蝶の紹介
季節型がある蝶として5種類の蝶を紹介します。
【季節型がある蝶の事例①】サカハチチョウ


サカハチチョウの春型と夏型の模様の違いは非常に顕著に表れます。
上の写真がサカハチチョウの春型と夏型です。春型は橙色の模様が目立つのに対して、夏型では白帯が明確となります。春型の次の世代が夏型となり、夏型の次の世代が年を跨いで春型になります。
なお、サカハチチョウとほぼ同じ見た目のアカマダラ(北海道にのみ生息)も、春型と夏型で同様の模様となります。
【季節型がある蝶の事例②】アゲハチョウ


よく見かけるアゲハチョウも春型と夏型があります。アゲハチョウに限らず、クロアゲハやカラスアゲハなど、多くのアゲハチョウ科の蝶は同様の特徴を持っています。
上の写真がアゲハチョウの春型と夏型の写真です。春型は夏型と比べて色が鮮明であるのと、小型になる傾向があります。アゲハチョウは年に4~5回程度の世代交代を繰り返しますが、そのうちの第1化が春型と呼ばれ、第2化以降を夏型と呼びます。
第1化の春型は3~5月頃に成虫となります。
【季節型がある蝶の事例③】ミヤマカラスアゲハ

ミヤマカラスアゲハをはじめ、黒いアゲハチョウ科の蝶も春型と夏型で違いがあります。最も違う点が大きさです。基本的に春型は小型、夏型は小型になります。また、ミヤマカラスアゲハは夏型と比較して春型は青緑色の輝きが強くなります。
【季節型がある蝶の事例④】トラフシジミ


トラフシジミも春型と夏型の差異が大きい蝶です。春型は裏面の白色が明確となり、夏型は褐色になる傾向があります。
【季節型がある蝶の事例⑤】キタテハ


キタテハは夏型と秋型で模様が異なります。越冬する個体は秋型となり、秋型は翅の表が赤っぽい色となります。夏型と秋型では生態も異なり、夏型は成虫の寿命が1か月程度であるのに対して、秋型は2~6か月程度と長く、越冬に適応した特徴を持っています。
蝶の季節型を決める要因
蝶の季節型が、どの様な生態的意義を持っているのかは現在のところよくわかっていません。
一方で、季節型を決める要因についてはこれまで多くの研究が行われています。中でも最もよく研究されているのがキタテハです。キタテハは、成虫で越冬し、年に4~5回程度の発生を繰り返し、越冬する個体が秋型となり、夏型と比べて翅の模様や生理的な特徴が異なります。
季節型が決定される要因は、主に4~5齢幼虫の時に浴びる日の長さです。1日に浴びる日の長さが13時間以下であれば秋型に、13時間以上となる場合は夏型となる傾向があります。このほか、気温も夏型と秋型の決定要因となることが確かめられています。
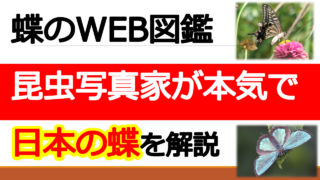
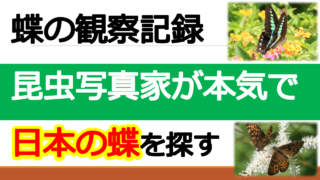
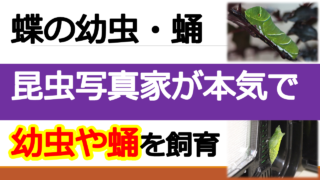
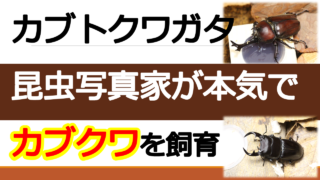



コメント